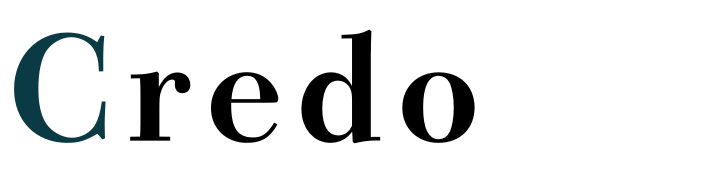命を守ることの意義とは
「動物の命を守ることには、どんな意味があるのだろう?」
「命を感じるというのは、一体どういうことなんだろう?」
そんな問いに、私はこう答えたいと思っています。
それはきっと、自分の人生を深く豊かにしながら、世界に“本当のやさしさ”と“生きる力”を、そっと広げていく行為なんだと。
私は小さい頃から、あらゆる生きものを身近に感じて生きてきました。
田んぼのそばで育った私は、バッタを捕まえて遊んだり、トンボやダンゴムシ、てんとう虫たちと、日常のなかでふれ合っていました。
てんとう虫をペットのように育てようとしたこともあります(すぐに飛んで行ってしまったけれど)。
水族館で見た魚の群れの美しさや、ヒヨコ、ウサギなどふわふわした動物たちとのふれあい。
そうした体験は、子どもだった私の心に癒しや驚き、感動と豊かさをたくさん与えてくれました。
飼っていたハムスターや金魚との暮らしのなかでは、
「餌をあげて喜んでもらえる嬉しさ」や「命をお世話する責任と大変さ」、
そして「別れの悲しさ」や「喪失の痛み」も教えてもらいました。
大人になってからは、ヒョウモンリクガメの“がじろう”、そして今は、祖母から引き取った犬の“しろ”と暮らしています。
社会人としてペットショップや牧場でも働き、子犬や子猫、牛たちの命とも関わってきました。
私が与えてきたつもりだった命との関わりは、振り返れば、
むしろ動物たちからたくさんの感情や気づき、心の豊かさをもらっていたように思います。
子どもの頃は、命の重みを深くは理解していませんでした。
ときに無自覚に、残酷だったこともあったかもしれません。
でも、大人になり、動物たちとの出会いを重ねていくなかで、
「命ってなんだろう」と、自然と考えるようになりました。
ふり返ってみると、彼らは「飼っていた存在」ではなく、
心をふわっとほどいてくれる安らぎや、前に進むための生きる勇気を教えてくれた、かけがえのない存在でした。
命にふれることで、あたたかさや切なさを知ることができる。
そして、「私たちは誰かの命とつながって生きている」ことを、実感できるようになる。
その気づきを与えてくれたからこそ、私はいま、こうして言葉を綴っているのだと思います。
過去のすべての出会いが、いまの私の土台になり、これから先の未来へとつながる希望になっています。
そして、このコラムを読んでくださった誰かの心に、
少しでも「何かが届いた」と感じていただけたのなら——
それは、ひとつの命が、別の命にそっと触れた小さな証なのかもしれません。
そうであったなら、こんなに嬉しいことはありません。
殺処分寸前だったウサギが教えてくれた、命と心の物語
殺処分寸前だった命との出会い
私の友人に、先日まで一羽のウサギと暮らしていた人がいます。
そのウサギは、保護施設に引き取られていた子で、あと数日で殺処分される予定だったそうです。
初めてそのウサギと出会った瞬間、彼女は「この子を助けなきゃ」と直感で感じたと言います。
ウサギを飼うのは初めてだったけれど、迷いはなかったそうです。
名前は「月光」と書いてつきみ。
満月の日に、一緒に暮らし始めたからだそうです。
最初の頃、月光(つきみ)は人との距離を測るような、不安げな様子をしていたそうです。
触れられることも苦手で、まるで警戒心の塊のようだったといいます。
きっと、保護されるまでに辛い経験をしてきたのかもしれません。
それでも友人は、毎日丁寧にお世話を続けました。
ごはんをあげる。
おしっこやうんちをこまめに取り除く。
ケージの中をきれいに保つ。
時間があるときは、そっと撫でて、声をかけてあげる。
心を込めた日々の積み重ねが、月光(つきみ)の心を少しずつほどいていったのです。
変わっていく表情と信頼
私が驚いたのは、写真に写る月光(つきみ)の表情の変化でした。
引き取られたばかりの頃の写真は、どこか怯えたような目をしていました。
でも、数ヶ月後に見せてもらった写真では、まるで別のウサギのように、柔らかくて穏やかな雰囲気をまとっていたのです。
心から安心しきった顔をしていました。
「こんなにも、ウサギの表情って変わるんだ」
「こんなにも、愛情って通じるんだ」
そのことに私は深く感動しました。
月光(つきみ)はいつしか、家族の中でもとりわけ友人に懐くようになったそうです。
誰が自分に愛情を注いでくれているか、ちゃんとわかっていたのでしょう。
「大好きだよ」「もっと撫でて」と言わんばかりに、毎日そっと寄り添ってきたと話してくれました。
月光(つきみ)が教えてくれたこと
しかし先日、月光(つきみ)は寿命を迎え、旅立ったそうです。
友人からの電話でその報せを聞いたとき、心の奥に、静かな寂しさがそっと滲んできました。
「お世話って、かわいいだけじゃなかったよ」
「ごはんを用意することも、毎日のおしっこやうんちの掃除も、本当に手間がかかった」
「でもね、不思議とそれが全部、愛おしかったの」
「たとえ汚れても、どんなに忙しくても、全部が愛おしくて、本当に大好きで、愛してたって思うの」
彼女はそう語ってくれました。
私はその言葉に、涙が込み上げました。
“きれいなことだけが愛じゃない”
“命を迎えるって、そういうことなんだ”
そう教えてもらった気がしました。
月光(つきみ)が保護されるまでの過去はわかりません。
でも、彼女と出会って、たくさんの愛情を受けて、安心して生きる時間を持てた。
それはきっと、月光(つきみ)にとってもかけがえのない幸せだったと思います。
命と命がふれあうとき、
そこには、言葉を超えた「通い合い」が生まれます。
月光(つきみ)が教えてくれたこのあたたかな物語を、これからも大切に抱きながら、必要な誰かにそっと届けていけたらと思います。
命を迎えるということ
命を迎えるということは、特別な誰かだけの話ではありません。
もしかしたら、あなたのもとにも、心を通わせる命との出会いが訪れるかもしれません。
しかし、その命は、ただ“かわいい”だけでしょうか?
私たちは、どこまで命の声に耳を傾けているでしょうか。
感情を持ち、知性を持つ動物たちが、今もなお見えないところで犠牲になっている現実があります。
命を「買う」こと、「捨てる」こと、「数で管理する」こと。
その仕組みを支えているのは、私たちの“知らなさ”かもしれません。
だからこそ、いま一度立ち止まって、
命との向き合い方、私たち一人ひとりの選択について、考えてみませんか。
科学が証明し始めた“動物の心と知性”——今、私たちに問われていること
月光(つきみ)のように、動物と心を通わせた経験を持つ人は、きっと感じているはずです。
「この子にも、ちゃんと感情がある」
「思っていた以上に、伝わってくるものがある」と。
でも一方で、「話せないからわからない」「感情なんてない」という声が、まだ社会には根強く残っています。
しかし今、国内外の研究により、動物の感情や知性が科学的に次々と明らかになってきているのです。
知性と感情を備えた、動物たちの本当の姿
〈犬/150語以上を理解し、人の感情に反応する〉
カナダの心理学者スタンリー・コレン博士によれば、犬は150〜200語の単語を理解し、5歳児相当の社会的理解力を持つといわれています。
飼い主の声や表情から感情を読み取り、共に寄り添う力も確認されています。
→出典:Stanley Coren, The Intelligence of Dogs(Free Press)
〈ブタ/人間の3歳児相当のIQと社会性〉
鏡で自分を認識したり、迷路を記憶する能力。仲間を識別する社会的記憶力。
人間の3歳児に近い知性を備えた存在として、世界中で注目されています。
→ 出典:Lori Marino & Christina M. Colvin, “Thinking Pigs” (Journal of Animal Cognition, 2015)
〈ゾウ/死を悼み、共感する心〉
亡骸に静かに寄り添い、骨に触れ、涙を流すような行動が確認されています。
ゾウたちは「喪失」や「悲しみ」を、言葉を超えて受け止めているのかもしれません。
→ 出典:Cynthia Moss, “Elephant Memories” (University of Chicago Press)
〈カメ/数千kmの帰巣本能と記憶〉
海を越えて何年も前に産卵した浜に戻る——そのナビゲーション能力は、科学的にも驚異的です。
地磁気や潮流の情報を脳に蓄え、「あの浜」を記憶していることが、最新の研究でも明らかになっているのです。
→ 出典:University of North Carolina, “Sea Turtle Navigation”, 2021
〈心があるのは人間だけではない〉
京都大学の研究チームは、マカクザルが「他者の感情に共感する脳活動」を示したと発表。
同時にハーバード大学も、「非人間動物にも共感や感情処理の神経構造がある」とする論文を発表しました。
また、哺乳類や鳥類の脳内に、他者の痛みやストレスを感じ取る神経構造があることが確認されたのです。
いまや、「動物に心がある」は、優しさではなく、研究で裏付けられた事実になりつつあります。
→出典:出典:京都大学霊長類研究所(2023年共同発表)、Harvard University, Department of Psychology, “Empathy and Emotional Processing in Nonhuman Animals” (2023)
それでも、動物が「モノ」とされる社会
けれど、日本の法律では、動物はいまだ「物」として扱われる場面があります。
動物を傷つけても、適用されるのは「器物損壊罪」。
命を奪われた存在に対して、“モノ”と同じ罪名がついてしまうことがあるのです。
(刑法261条/環境省ガイドラインより)
2023年、全国で動物虐待で摘発されたのは211件。
そのうち起訴に至ったのは、約50件程度にとどまっています。
「命としての尊重」ではなく、「所有物としての扱い」が優先される。
この現実は、法律だけでなく、社会全体の価値観が問われていることを意味します。
密猟の犠牲になる命と、日本の関わり
〈象牙のために命を落とすゾウ〉
アフリカでは今も象牙を狙った密猟が続き、群れで生きるゾウたちが命を落としています。
日本は、家庭内にある象牙の再流通が可能な数少ない国として、国際的な非難を受けています。
(日本の象牙保有量:約280トン/TRAFFIC・WWF 2024年報告)
〈密輸される動物たち〉
日本の空港では、年間2,000件以上の違法な野生動物の押収が行われています。
リクガメ、トカゲ、インコ——彼らの多くは、過酷な環境で輸送中に命を落としています。
「ペットとして飼いたい」と思う気持ちが、
知らず知らずのうちに「密猟の加担者」になることがあります。
〈マイクロブタ/“流行”で捨てられる命〉
ここ数年、SNSで「かわいい」と話題になったマイクロブタ。
東京や大阪では「ブタカフェ」も人気を集め、一時は飼育希望者が急増しました。
でも実際には、マイクロブタは成長すると20〜40kgにまで大きくなる個体もおり、
「大きくなりすぎた」「思っていたのと違う」「鳴き声がうるさい」「部屋が汚れる」といった理由で手放されるケースが後を絶ちません。
2022年には、東京都内の保護団体が受け入れたマイクロブタの数が前年比1.8倍に。
その多くが、飼育開始から1年以内に放棄されていたそうです。
→出典:NPO法人しっぽの会/東京都動物愛護推進員協議会 調べ
動物保護と自然環境/命を守ることは、未来を守ること
動物を大切にすることは、自然環境との調和を育むこと。
それは、私たちの暮らしや地球の未来にも深く関わっています。
たとえば、
・熱帯雨林の破壊は、野生動物のすみかを奪い、気候にも影響を及ぼします。
・密猟や違法取引は、生態系のバランスを崩し、やがて人間の暮らしにも影響を与えます。
命は、姿かたちや種類にかかわらず、すべてかけがえのない存在。
私たち一人ひとりの思いやりが、社会や自然のあり方を少しずつ変えていきます。
未来をかたちづくるのは、特別な誰かではなく、
日常の中で小さな気づきから行動を起こす、一人ひとりの力です。
〈これからの社会に必要な7つの視点〉
①動物を「物」ではなく「命」として扱う法律
②ペットの飼い主教育の義務化
③保護団体への公的支援
④ブリーダーやショップの透明化と規制強化
⑤保護活動を支える制度の整備
⑥命の現実を伝える教育とメディアの役割
⑦寄付やボランティアなど、多様な関わり方の広がり
〈今日からできる、小さなアクション〉
①保護団体への寄付や物資支援
②SNSで課題をシェアする
③保護犬や猫を迎えるという選択肢を知る
④子どもに命の話をする
⑤エシカルな商品や寄付先を選ぶ
⑥「本当に飼えるか?」を問い直す
⑦命の背景を知り、想像してみる
どんなことも、はじめはほんのわずかな行動から。
日常の選択が、未来をあたたかく照らす力になります。
命と心に向き合う。それは、自分を大切に生きるということ
命に寄り添い、助けようとする気持ちは、
人間だからこそ持てる、かけがえのない力です。
本来、誰の中にもあるその優しさは、
自分自身を大切にすることにも、きっとつながっていきます。
命と向き合う姿勢は、自分の生き方を映す鏡のようなもの。
日々の小さな選択が、自分を知り、他者を思いやる力を育ててくれます。
命を守るという選択は、
誰かの命を救うと同時に、あなた自身の“生きる力”にもなっていくはずです。
その一歩が、命をつなぎ、社会に調和と思いやりの輪が広がっていく。
そんな未来を、あなたと共につくっていけたらと、心から願っています。