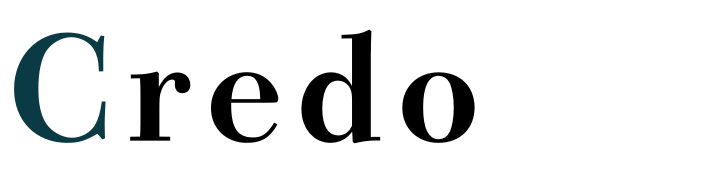こんにちは、naoです。
先日、話題になっている映画『国宝』を観てきました。
ひとりの歌舞伎役者の50年を描いた壮大な物語で、「命の輝き」
そのすべてが心にも体にも響き渡るように、
この映画には、3時間という長さをまったく感じさせない、
めまぐるしくも淡々と進んでいく出来事の連なりと、
その静と動が幾重にも重なり合う世界の中で、
舞台に立つ者の、狂気にも似た覚悟。
生きることの苦しさも、死を背負って立つ重さも、
すべてが、
その瞬間、まるで視線を絡め取られたように、
『国宝』は、ただの映画じゃない、、!!
命を燃やして芸を極め、運命に翻弄されもがきながらも、
そんな生と死の狭間にひそむ、
観終わったあとの静けさの中で、
「生きる」って、なんて苦しくて、
そう思わせる3時間。ただただ、
舞台を体験するような3時間
「映画を観た」というより、「舞台を体験した」
正直、これまで日本映画を観たときに、「あぁ、
でも、その心配はほんの数分で消えていました。
心の底からそう願っていました。
そして何がすごいって、私が観た時には公開から2ヶ月以上、
空席がほぼ見当たらなくて、人がぎっしり。
その光景を目の前にして、「あぁ、みんな“何か”
吉沢亮さんの“狂気”のすごみ
主演の吉沢亮さんのお芝居は、「美しい」、「かっこいい」、、
演じることを超えて、役そのものとしてそこに在る。
その姿は、
この体感は、この映画に触れた人だけが分かるものだと思います。
横浜流星さんの“熱”と“繊細さ”
そして、横浜流星さん。
彼が演じる大垣俊介の、まっすぐで純粋な優しさ。
その奥に隠された、吉沢亮さんが演じる立花喜久雄への憧れと、
そのすべてが交じり合った複雑な感情が、苦しいほど、
その“人間味”を余すことなく表現できる横浜さんの演技力に、
ふたりの演技は、“演じている”という領域を完全に超え、
ふたりが並んだその空気感は、役としても、俳優としても、“
国宝という物語が描く二人の人間の交差する数奇な縁と、
その不思議で神秘的な世界観が、
田中泯さんの存在感
そして、田中泯さん。
泯さんが現れた瞬間、スクリーンの向こうの世界が、
言葉にしようとすることさえ、どこか野暮に思えるような。
ただ、そこに“存在する”だけで空気が変わる。
人間国宝を演じていると頭では分かっていても、「そうなのだ」
人間国宝として舞台に立つ、その歌舞伎のシーンは、
歌舞伎のことに詳しいわけじゃないのに、
ただ、「すごい」としか言えない。魂が喜ぶって、
あの場面がたっぷり描かれていたのが本当に嬉しくて、「
そして、劇中には名シーンが本当にたくさんあるのですが、
あの場面は、もう最高に大好きです!
三浦貴大さん演じる竹野が、「あの婆さん、、いや、じいさんか。
あれがもう、たまらなくて。笑
本当にそうなんですよ。笑
映画の中で、“婆さんにしか見えないじいさん”
また、病床に伏した万菊さんを演じるシーンも、
何がって、、万菊さんが、全然病人には見えないところ!(笑)
ベッドに横たわっているのに、
それでもやはり、泯さんのお芝居は素敵で、素晴らしくて。
そんな泯さんのシーンがたっぷり詰まった『国宝』
私が泯さんを最初に知ったのは、確か2023年のドラマ『
正直、田中泯さんという俳優に、もっと早く気づきたかったな、
そして今作でも、泯さんの底知れない魅力に、
田中泯さんは、世界的な舞踊家であり、唯一無二の俳優。
80歳を迎えた今も、
『国宝』を観ながら、改めて思いました。
田中泯さんって、本当にすごい。
オーラっていうのかな、エネルギーっていうのかな。とにかく、
「こんな方、まだこの時代にいたんだ、、」と、
“ラッキー”なんて言葉じゃ軽すぎて、足りないのだけど、
私にとっては、それくらい“すごい存在”です。
この映画で、泯さんが演じる歌舞伎を観られたこと、
作品全体が“ひとつのイキモノ”だった
『国宝』を通して感じたのは、役者もスタッフも、
3時間の物語が、
そんな感覚でした。
井口理さんが放つ、音楽の衝撃
そして最後の最後、エンドロールで流れた井口理さんの歌声。
全身がクァアアアアアッと目醒めるように、魂ごと痺れました!!
映画のラストまで揺さぶられ続けた心に届く、
まるで映画全体を優しく包み込んで、
井口理という才能は、本当にすごい。
その歌声のひとつひとつが心と身体にすっと入り込み、
その声が持つ振動とエネルギーに、改めて“音”
波動って、目には見えないけれど
やはり存在しますよね。
歌舞伎が心を震わせる理由
歌舞伎という日本文化のことはもちろん知っていたけれど、
けれど、この映画を観ながら、「あ、
この映画で物語の中心にあるのは、女方(おんながた)
江戸時代、
男性が女性を演じる、それは、
そんな背景を知ってから見ると、
歌舞伎が人を惹きつける理由は、
「完璧な型」と「溢れ出す感情」、その両方が絡み合い、
それは、きっと日本人として体の奥に刻まれた記憶や感覚が、
歌舞伎が心を揺さぶる理由、それは、
芸術が灯す、生きる力
映画を観ていて、ふと思ったのです。
人は誰もが、こうした“魂を震わせる体験”を、
今の日本では、「生きがいが見つからない」「
それは、誰の心にも積もってしまう、
そんな時代だからこそ、
それは、生きる力や、「もう一度、明日をがんばろう」
芸術は、ただ「きれい」「楽しい」で終わるものではなく、
映画『国宝』を観ながら、そのことを何度も強く感じました。
日本人の感性の誇り
実は同じタイミングで、話題の映画『鬼滅の刃 無限城編』も観てきたのです。
あの圧倒的な映像美と熱量、
今回観た『国宝』、そして『鬼滅の刃』。
最近話題の映画2本を観て、改めて思ったのです。
日本人の感性って、本当にすごい。
日本のカルチャーには、目には見えない「心」
繊細で、緻密で、情熱的で、でもどこか風情があって。
この美意識は、
私にとって、こうした文化や芸術はただの“好き”ではなく、
心が揺れ動く瞬間が、私を私らしく生かし続けてくれています。
そして感動は、生きるためのエネルギー。
芸術や文化に触れることは、その“命のガソリン”
心が疲れていても、何かを見て魂が震える瞬間があれば、
でも、芸術に触れることって、
美術館に行くとか、舞台を観に行くとか、
朝、カーテン越しに差し込む光を見つめること。
道端の小さな花に気づくこと。
ふと流れてきた曲に、心がふわっと動くこと。
『国宝』を観て映画館を出るとき、日常に散りばめられている、
心を震わせる体験、魂が揺さぶられる時間、そして「生きる」
そのすべてが、この映画には詰まっています。
もしまだ観ていない人がいたら、
これは、ただの映画ではなく、
私たちの日常に、突如出現した歴史的ワンシーンです。
そして、令和を代表する映画だということは間違いないでしょう。
『国宝』は、あなたの心の奥深くに眠る「何か」
私も、自分の命をもっと楽しみ、生き抜きます!
今日もあなたがあなたであることを、ここに称えて。
さぁ、自分じゃないものを手放し、思いっきり生きて参りましょう。