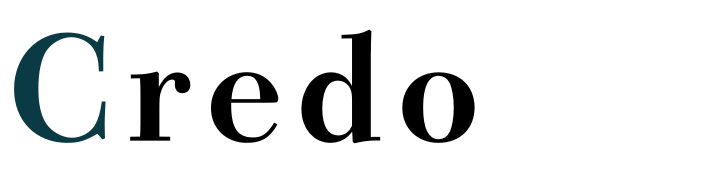山形美術館に着いたその日、まず驚いたのは人の多さでした。
駐車場はすでにいっぱいで、
美術館の前には長い列ができていて、
「美術館って、こんなに人が集まる場所だったかな?」
その光景に出会ったとき、心がワクワクしました。
山形美術館は、常設展示の作品にもたくさんの魅力があって、
思い返せば、
あのときも会場は熱気に包まれ、作品の前で立ち止まり、
アートが生活に溶け込み、人々の心を照らす瞬間を、
今回の古代エジプト美術館展も、
でもそれは、単なる人気イベントだからではなく、、
そこには、人々が無意識に求めている「何か」
「山形のみんな、こんなにエジプトが好きだったの?」
そんな冗談めいた感想を抱きながらも、私自身もその「何か」
そう気づいた瞬間、美術館という空間が一層愛おしく思えました。
棺とミイラが語りかけるもの
展示室に入ると、目に飛び込んできたのはミイラや人型木棺。
その存在感は圧倒的で、単なる「遺物」ではなく、
棺の装飾には、死者が無事に冥界を旅し、
古代エジプトの棺には、オシリスやアヌビスといった神々、
それらはどれも「生と死をつなぐアート」として、
古代エジプト人にとって、
《肉体は滅んでも魂は永遠に生きる》、そう信じたからこそ、
ツタンカーメンの小さな指輪を目にしたときも、
一見ただの装飾品に見えるその指輪は、王の存在を象徴し、
小さな造形物であっても、アートには「
そして、そのアートには「命の証」
数千年を超えてなお、《ここに確かに命があった》、
まるで時間を超えて交わされる対話のように。
神話が教えてくれる死と再生の思想
展示を見ながら、私はエジプト神話のいくつかを思い出しました。
たとえば、オシリス神話。
冥界の王オシリスは弟に殺されても、
「死んでも終わりではない。魂は愛と祈りによって再生する」
その象徴として語り継がれてきた物語。
この物語が伝えているのは、ただの慰めではなく、
肉体は滅んでも、魂は永遠に生き続ける。
そう信じる力こそが、古代の人々にとっての希望であり、
そして太陽神ラーの旅。
ラーは昼は空を舟で渡り、夜は冥界を航行し、翌朝また昇る。
昼と夜を繰り返し、光と闇を往復しながら、
その思想は「闇の後には必ず光が来る」
また、「死者の書」に描かれる審判の場面。
死者はオシリスの前に立ち、心臓を天秤にかけられます。
もし真理の羽よりも軽ければ、魂は永遠に生きられる。
けれど重ければ滅びてしまう。
その寓話は、現代に生きる私たちにも問いかけてきます。
「あなたの心は、今どれだけ軽やかですか?」
「あなたの生き方は、魂を輝かせていますか?」
古代エジプトの神話やアートは、単なる過去の文化財ではなく、
そしてそこにこそ、アートの存在意義があります。
なぜ人は古代エジプト展に惹かれるのか
会場を歩きながら、ふと考えました。
「なぜこんなに多くの人が古代エジプトに惹かれているのだろう?
もちろん、ツタンカーメンやミイラといった“
けれど、それだけでは説明しきれない強い吸引力があった、
そしてそれはおそらく、
古代エジプト人は、太陽の運行に合わせて神殿を建て、
そこには「生きる意味」「死の先にあるもの」
現代社会は、効率や合理性ばかりが重んじられ、
だからこそ人々は無意識に、“心を整える時間”や“
最近、
それだけ需要が高まっているからこそであり、
古代エジプト展に足を運んだ人たちは、
むしろ「自分の心を思い出すため」
アートの存在意義を考える
展示を見ながら、
古代エジプトの棺や壁画は、
そこには「自分の命の存在意義」への問いかけや願い、
《命をどう生きるのか》
自分の存在を見つめ、
現代に生きる私たちにとっても、アートの意味は変わりません。
アートは、言葉では表せない想いを形にするもの。
心の奥に眠る感情を解き放ち、誰かと分かち合うことで、『
よく「アートは生活必需品ではない」と言われますが、私は、
アートは、目に見えないけれど、人の心を動かしてくれます。
現代はあふれる情報やめまぐるしいスピードの中で、
だからこそ、感情を解き放ち整えてくれるアートは必要なのです。
古代エジプト展を通して、私は改めて「アートは暮らしに必要だ」
美術館で交わされるエネルギー
会場を歩きながら感じたのは、
棺をじっと見つめていると、その背後に広がる景色や、
装飾品や化粧容器を見れば、数千年前の誰かの願いがよみがえり、
これは単なる鑑賞体験ではなく、
展示物から受け取る力があると同時に、
だからこそ、会場を後にする人々の顔には、
その表情を見て、私は、
人はみな、この美術館で「自分だけの宝物」を見つけて、
それは言葉にならないものかもしれません。
けれど確実に、自分の中で静かに光を放ち始め、
美術館やアートには、そんな力が宿っているのです。
結び──アートは未来を照らす光
古代エジプト展を後にしたあと、
歩きながら、さっきまで見てきた棺やミイラ、
それらが放つエネルギーは、数千年という時間を越えて、
そのとき、胸の奥から浮かんできた想いがあります。
古代エジプトの展示品の数々は、
そして、日本の八百万の神という概念があるように、
古代エジプト人が祈りを、壁画や装飾品、アートに込めたように、
「これを見た人が、自分の命の光を思い出せますように」
人生は、自分の中の喜びに出会う旅だから。
あなたが、あなたで在れますようにと、願いを込めて。
展覧会で出会った人々の姿がとても印象的でした。
棺の前でじっと立ち止まり、静かに見入る人。
装飾品の細やかな模様に目を凝らしている人。
展示解説に視線を走らせながら、何度も作品を見直す人。
彼らはきっと、それぞれの心に光を見つけたはずです。
それは知識や情報を得ること以上に、
そしてそれこそが、美術館の存在意義。
展示物やアートはただの鑑賞対象ではなく、
あなたの中に眠るアートへ
今回の山形美術館「古代エジプト美術館展」は、
駐車場があふれ、人が列を作り、
それは、古代エジプトという文明が放つ圧倒的で神秘的な力、
展示されたミイラや棺、壁画や装飾品は、
オシリス神話やラーの旅、「死者の書」に描かれた死生観は、
人々はこの展覧会で、自分の中に眠っていた命の光に気付き、
そしてそれは、一人ひとりの「未来を生きる力」
美術館を訪れることは、自分の命を深呼吸させ、
それは、日々を生きるために欠かせないもの。
心を養い、魂を支えるものなのです。
私も一人のアーティストとして、
アートに触れることで、
美術館での体験がそうであったように、