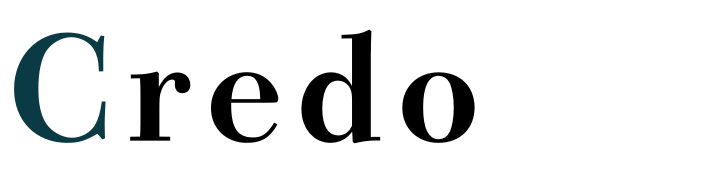小さな幸せと社会とのつながりがあなたの人生を豊かにする
皆さん、こんにちは。イギリス在住のジェーン彩です。
イギリスと聞くと、皆さんはどんな印象をお持ちでしょうか。赤い二階建てバス、霧に包まれた街並み、あるいは紅茶や王室のイメージかもしれません。中にはロイヤルファミリーが象徴する「階級社会」という言葉を思い浮かべる方もいるかもしれません。
実際に暮らしてみると、確かに今でもイギリス社会には階級の名残が見え隠れします。直接的に差別をするようなことはなくても、生まれ育った環境や家柄によって、将来の選択肢がある程度決まってしまう現実があることもしばしば。
けれどその一方で、私が強く感じるのは、イギリスの人々が「自分の小さな幸せをしっかりかみしめている」ということです。
イギリスは階級社会の影響もあり、「努力すれば必ず上に行ける」とは限らない現実があります。だからこそ彼らは、今ある日常の喜びに目を向ける習慣を自然と身につけてきたのかもしれません。
一方で、日本社会は「頑張れば報われる」という言葉を信じて、がむしゃらに走り続けてきた人が多いのではないでしょうか。その過程で、かえって「自分にとっての小さな幸せ」を見逃してきた人も少なくないかもしれません。
「大きな夢や目標を叶えること」も大事だけれど、「今日のひとときをどう楽しむか」に目を向ける。制約がある中で生きてきたイギリス人だからこそ、日常の中にある喜びを見逃さない。それが彼らのしたたかさであり、魅力なのかもしれません。
今回は、そんなイギリスで学んだ「小さな幸せの見つけ方」を3つに絞ってご紹介します。
自然との共生、市民が勝ち取った「フォレストウォーク」

日本人にとってイギリスといえばロンドンの景色を思い浮かべがちですが、実は地方ごとにまったく違う表情があります。
- 絵本のようなコッツウォルズの田園風景
- 詩人や作家たちが愛した湖水地方
- 雄大な景観が広がるスコットランド
- 自然と歴史が共存するウェールズの海辺や山々
- 街の中心には必ず教会があり、地域ごとの「暮らしのにおい」が漂うパブ があります。
どこを切り取っても絵になる、イギリスらしい郊外の景色が私は大好きです。
そして、イギリス人にとって家族や友人と大切な時間を過ごす場所の一つが「森」。週末に訪れるフォレストウォークは、なんとも贅沢なひとときです。
なぜ贅沢かというと、遡ること中世イギリスでは、広大な森や土地は領主や貴族、王室の所有物でした。産業革命期の「エンクロージャー(囲い込み)」では、庶民が森で薪を拾う・放牧する・道を歩くといった権利もどんどん失われていきました。
そこから市民運動が起こり、時間をかけて「森や丘を歩く自由」を取り戻していきました。つまり、自然を楽しむ庶民の権利は歴史的に勝ち取ってきた成果なんです。
現代では当たり前のように歩ける森も、背景にはこうした歴史があります。イギリスには自然保護区(nature reserve)が多く存在し、国を挙げて自然保護に取り組んでいます。
静かな森を歩きながら季節の植物に触れ、会話を楽しむひととき。デジタル社会に生きる私たちにとっては、強制的にデジタルデトックスできる時間でもあります。
何かにつけて、とりあえず紅茶
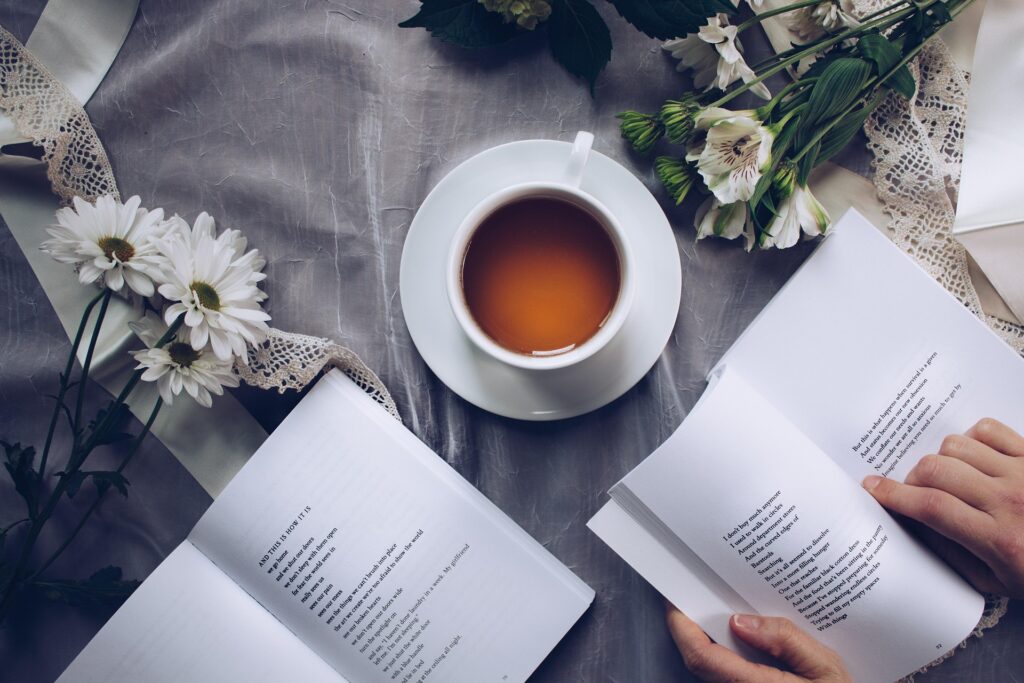
イギリス人の国民的な飲み物といえば「紅茶」。
素敵なティーセットでいただく紅茶もあれば、大きなマグカップにティーバッグを入れるだけのラフな飲み方も一般的です。
私もイギリスに来て「一体この人たちは何杯紅茶を飲むのか」と驚きました。コーヒー派だった私も、今では紅茶をよく飲むようになっています。
朝起きて、休憩時間に、何かイライラした時に、リラックスする時に。彼らの側には必ず「紅茶」があります。
スーパーの紅茶売り場は壁一面にずらり。イングリッシュブレックファーストが最も一般的ですが、その種類の豊富さには圧倒されます。
ある調査によると、イギリスでは国民総消費量が 1日あたり約1億杯。1人あたり毎日2杯程度、年間で約360億杯にもなります。
しかも朝だけで5300万杯。半数以上の人が「紅茶を飲まないと一日が始まらない」と感じているそうです。
私がイギリスで務めていた会社でも、始業後に紅茶を入れる人が多く、内心「始業前に淹れないの?」と思ったほど。それくらい紅茶は欠かせない存在なんです。
18世紀には医療飲料として宣伝されていた歴史もあり、砂糖と共に飲むことで下水由来の病気対策になったとも言われています。まさに「命を守る一杯」でもあったわけです。
ちなみに紅茶文化といえば「アフタヌーンティー」。これは1840年代に貴族のご婦人が、夕食までの空腹をしのぐために紅茶と軽食をふるまったのが始まりだとされています。
皆さんは、リラックスするときに何を召し上がりますか?
チャリティーショップで宝探し

イギリスでは「チャリティーショップ」というリサイクルショップのようなお店がたくさんあります。売上は支援団体へ寄付される仕組みで、がん研究・子ども支援・動物保護・ホームレス支援など多様な分野をサポートしています。
有名なのは“Oxfam”。第二次大戦後にオックスフォード大学関係者が立ち上げた「飢餓救済委員会」が起源で、今では90カ国以上で活動しています。
チャリティーショップでは衣料品、食器、小物、アクセサリー、おもちゃなど様々なものが並びます。思いがけない掘り出し物を見つけるのも楽しみのひとつです。
しかも、買い物がそのまま寄付につながるので「気持ちよくお買い物できる」のも魅力です。不要品を寄付することもでき、モノが循環して社会に還元されていきます。
さらにイギリスでは、セカンドハンド品を「中古」とは捉えず、歴史やストーリーが宿るものと考えます。使い込まれた食器や家具、誰かが袖を通した服にも暮らしや思いが込められている。それが価値だと受け止められているのです。
こうした文化に子どもの頃から触れることで、イギリスの子どもたちは自然と「社会貢献」の大切さを学んでいきます。寄付やボランティアは幸福度を高めるとも研究で示されており、「誰かのために行動することが自分の喜びにつながる」と多くの人が実感しています。
まとめ
いかがでしたか?
イギリス人は、太陽の光が出たら森や公園を歩き、家族や友人と自然の中で語らう時間を大切にします。一日に何度も紅茶を淹れ、自分の気持ちをリセットし、チャリティーを通じて社会とつながりを感じる。
決して大げさではなく、日常にある「小さな幸せ」を一つひとつかみしめて生きています。
その姿は、効率や成果を優先しがちな私たち日本人に「大切なこと」を思い出させてくれます。大きな夢や目標を追うことも素晴らしいですが、その過程で心がすり減っては続きません。
むしろ日々の暮らしの中で見つけるささやかな喜びこそが、次の一歩を踏み出すエネルギーになるのではないでしょうか。
皆さんもぜひ、ご自身にとっての「小さな幸せ」をあらためて考えてみませんか。
今日の空の色でもいい、好きな飲み物でもいい、誰かとの短い会話でもいい。小さな幸せを自分で選び取り、自分のご機嫌を上手にとれる人は、きっとこれからの人生をもっと豊かに歩んでいけるはずです。