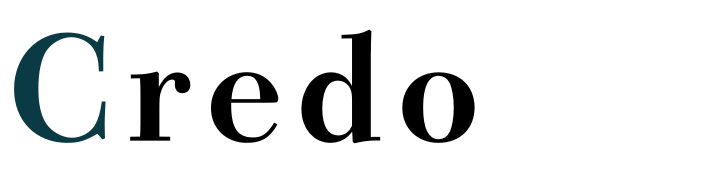こんにちは、naoです。
私が動物保護について、初めてコラムを書こうと思ったとき、最初に思い浮かんだのは、徳川綱吉でした。
江戸時代の五代将軍。あの「犬公方(いぬくぼう)」と呼ばれた人物です。
中学生の頃、歴史の授業で「生類憐れみの令=悪法」として習った記憶があります。
“犬を大事にしすぎて人を苦しめた将軍” そんなイメージのまま、大人になっていた私。
でも最近、調べ直してみてびっくりしたのです。
本当は、あの時代にしては驚くほど先進的な、「命を平等に守る」という想いから生まれた政策だったんだ、と。
綱吉という人 ― 優しさと複雑さ
綱吉は、徳川三代将軍・家光の三男として生まれました。
幼いころから聡明で、学問や仏教の教えに深く親しんでいたそうです。
ある日、母・桂昌院が「あなたは戌年だから、犬を大切にしなさい」と語ったという逸話が残っています。
この一言が、彼の中で「命を守る」という強い芯になったのかもしれません。
そして、将軍となった綱吉が打ち出したのが、あの有名な生類憐れみの令です。
犬だけでなく、猫、鳥、魚、さらには人間の赤ん坊や病人に至るまで、弱い命を守るための徹底した保護政策でした。
江戸の街に犬の楽園を作った将軍
当時の江戸の街には、野良犬がたくさんいました。
飢えや病気で苦しみ、人間に虐げられて命を落とす犬も少なくなかった時代です。
そんな状況を見た綱吉は、「命は平等だ」と考え、次々に手を打ちました。
たとえば、「御犬屋敷」という施設を作り、迷い犬や野良犬たちを保護。
餌を与え、怪我を治療し、安全な場所を提供したのです。
御犬屋敷には数千匹もの犬が暮らしていたといわれ、江戸の人々はその光景に驚いたそうです。
ただ、この政策は庶民には重く映る部分もありました。
「人間より犬が大事なのか」と批判されたり、誤解が広がったりもしました。
でも、その根っこにあったのは、「苦しまなくていい命を、苦しませない」という優しさだったのだと思います。
優しさの裏にあった孤独
綱吉の人生には、いつも孤独がありました。
将軍という立場ゆえの重圧、男子の世継ぎに恵まれなかった悩み、そして絶え間ない批判の声。
だからこそ、人の痛みが、誰よりもわかっていたのかもしれません。
命を大切にすることの重さや、その尊さを、誰よりも知っていたのではないでしょうか。
歴史を振り返ると、綱吉の政策は「やりすぎ」として語られることが多いですよね。
でも、視点を少し変えてみると見えてくるものがあります。
300年以上前に、すべての命を等しく大切にしようと本気で行動した人が、確かにここにいた、その事実に、胸が熱くなりました。
300年後のオランダで起きたこと
そんな綱吉を思い出しながら、最近、SNSでこんな投稿を目にしました。
2023年、オランダが短頭種犬(フレンチブルドッグやパグなど)の繁殖を制限する方針を強化したという話題です。
オランダでは2014年から動物保護法(Wet dieren)に基づき、健康を損なう外見を持つ犬や猫の繁殖を規制してきました。
2019年には「短頭種犬の基準」を具体的に定め、鼻の長さや呼吸音、頭蓋骨の形を細かくチェック。
基準を満たさない個体は、純血種であってもミックスであっても繁殖できない仕組みに。
そして2023年には、さらに所有や広告にも制限をかける方針を、大臣が公式に発表しました。
法律の根底にあるのは、「かわいい見た目よりも命の健康を優先する」という強い想いです。
“かわいい”の裏側
フレンチブルドッグやパグ、ブルドッグ。
その愛らしい姿はたくさんの人を魅了しますが、実は深刻な健康問題があります。
・英国Royal Veterinary Collegeの研究では、フレンチブルドッグの約45〜60%が呼吸障害(BOAS)を発症
・パグの30〜40%が角膜潰瘍などの眼疾患
・フレンチブルドッグの80%以上が帝王切開で出産
・猫では、スコティッシュフォールドの折れ耳が軟骨形成不全という遺伝性疾患の結果で、生涯関節痛に苦しむケースも
これは飼い方の問題ではなく、外見を極端に変えてきた繁殖そのものが原因です。
ミックス犬と健康 ― 遺伝の多様性
「ミックス犬は健康」という話を耳にしますが、正しくは“遺伝的多様性が高いことで病気のリスクが下がる傾向がある”ということ。
JAVMA(2013)の研究では、純血種よりも遺伝性疾患が少ないケースが多いと示されています。
ただし、これは適切な繁殖管理が前提です。
どんな犬でも、健康を最優先にした繁殖が欠かせません。
日本の現状
日本でも動物愛護法の整備が進んできましたが、オランダほど厳しい規制はまだありません。
短頭種や極小犬の繁殖を一律で禁止する法律はなく、マイクロチップの義務化や終生飼養の努力義務など、少しずつ環境が整ってきた段階です。
だからこそ、飼い主一人ひとりの選択が未来を変えるカギになります。
命を守るためにできること
・迎える前に、健康と福祉に関する情報を調べる
・健康を第一に考えるブリーダーや保護団体から迎える
・命を終生、大切に育てる覚悟を持つ
・外見だけを重視する広告やブームに流されない
おわりに
歴史って、本当に不思議です。
中学生のときに「悪法」と覚えたあの政策が、今の私には命を守るための行動として見えてきました。
時代が進んで研究が進む中で、新たにわかったことが増えて、見え方がまるで変わってきた。
何が正解かを決めつけずに、学び続けることの大切さを改めて感じます。
この綱吉の姿が本当なら、彼が守ろうとした想いを、未来を生きる私たちがちゃんと引き継いでいきたい、そう思います。
賛否両論を承知で、それでも命を守ることに本気で舵を切った、その“まなざし”に、とても心を掴まれました。
300年前の江戸から、今の私たちへ届いたメッセージ。
「命を軽んじない」というたったひとつの想いは、時代を越えても変わらないはずです。
オランダが示した“命を優先する選択”も、同じように未来へつながる光のひとつ。
私たちが日々の中で重ねる小さな選択が、やがて大きな力になっていく。
人も、動物たちも、もっと幸せに生きられる社会を、きっと私たちはつくっていける、そう信じています。